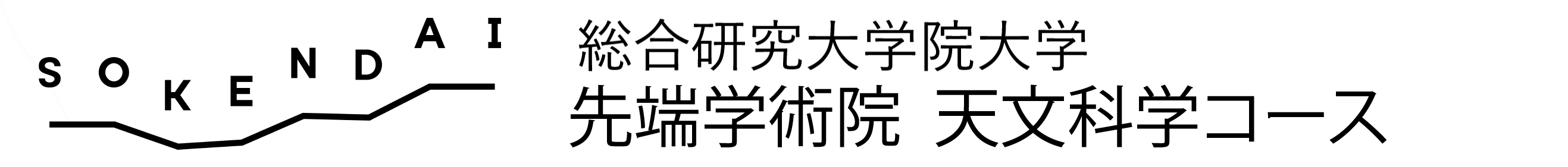- ホーム
- コース案内:
- 修了生の声
修了生の声
総合研究大学院大学数物科学研究科(1992年4月〜2004年3月)、物理科学研究科(2004年4月〜)を修了されて各界で活躍中の修了生の声を取り上げてみました。 ※肩書は掲載当時のものです
ハワイ観測所でスローライフを満喫しながら研究に没頭
嶋川里澄さん(国立天文台 ハワイ観測所 国立天文台フェロー、平成28年度総研大修了)
私は総研大の5年一貫制に入学し、5年のうち約半分をハワイ島ヒロにある国立天文台ハワイ観測所で過ごしました。ハワイ島は車で半日で一周できる小さな島ですが、ハワイ諸島の島では一番大きな島なのでビッグアイランドと呼ばれています。東京と比べれば何もない田舎ではありますが、ビッグアイランドと呼ぶにふさわしい雄大な自然が広がった場所でもあります。現地の方々は非常に温かく、気候も一年を通して日本の夏より涼しく冬はありませんのでスローライフを満喫しながら研究に没頭することができます。私は英語がもともと(今も)苦手なのですが、こちらで長く生活したことでアメリカ本土に滞在するときも比較的苦労なく過ごすことができるようになりました。
ハワイ島には日本が誇るすばる望遠鏡を始め様々な国の望遠鏡が主にマウナケア山にそびえています。そのためヒロ市内にある各望遠鏡の山麓施設ではいろんな国籍の天文学者が働いていますし、また各国から多くの観測者が来訪してきます。彼らと日々交流することで自らの知識・技能を高めるだけでなく卒業後に向けて国際的なつながりを作ることができます。ハワイ観測所には総研大の先生方【教員一覧】が多く在籍していますので、もしこの記事を見てハワイ島での研究に興味が湧きましたら是非コンタクトを取ってみて下さい。私を含め観測所の方々はいつでも次世代に続く若い力を歓迎しています。
研究の道に進む事を迷わなかったのは総研大と国立天文台がつくる環境のおかげ
大西響子さん(愛媛大学 宇宙進化研究センター 特定研究員、平成28年度総研大修了)

国立天文台に来て、総研大生として研究ができて良かったと思う事はたくさんありますが、大きく分けると三つになると思います。 一つ目は、大学院生という時期を研究機関で過ごせたことです。アルマ望遠鏡は今、世界で最も注目を集める結果を生み出している望遠鏡であると言っても過言ではなく、そのような望遠鏡の裏で行われている膨大な量の仕事を間近で見る事が出来たことは、自分の人生において非常に大きな財産となりました。また、研究機関ならではの環境として、学生を学生扱いせず研究者として対等に接してくれるスタッフが多く、研究とは何かという事を肌で感じて学ぶ事ができました。 二つ目は、資金が潤沢である事です。研究活動を行う上で、国際研究会に参加するための海外渡航費や論文投稿料などが必ず必要になりますが、国立天文台の総研大生としてそれらの資金で困る事はほとんどなく、研究に集中できる環境が整備されていると言えます。 三つ目は、様々な研究者と繋がりを持つことができる事です。研究の世界において人脈は非常に重要だと言えます。 国立天文台は、日本だけでなく世界から天文学の研究者が訪れる場所です。積極的にセミナー等に参加すれば、色々な研究者と気軽に議論ができます。色々な人に自分の研究を覚えてもらう事はとても大事な事であり、国立天文台という場所はそれを比較的簡単にしてくれます。
卒業後も研究の道に進む事を迷わなかったのは総研大と国立天文台がつくる環境のおかげだと思っています。研究者になる事を真剣に考えたい人に自信を持ってお勧めできる環境です。
国立天文台にて得た人的財産は現在の研究生活において大変重要
片岡章雅さん(ハイデルベルグ大学 理論天体物理研究所 日本学術振興会海外特別研究員、平成26年度総研大修了)

(総研大入学志願者向け広報誌より転載)
観測天文学の現場で鍛えられる
眞山聡さん(総合研究大学院大学 葉山キャンパス 講師、平成19年度総研大修了)
 当時参加したハワイ島でのJTTU宇宙教育プログラムにおいて。左端が筆者。JTTU(Journey Through The Universe)プログラムとは、ハワイ島の教育委員会、ハワイ島とアメリカ本土の研究機関が協力して行う、地元の学校への出前授業等を含む宇宙教育プログラムです。
当時参加したハワイ島でのJTTU宇宙教育プログラムにおいて。左端が筆者。JTTU(Journey Through The Universe)プログラムとは、ハワイ島の教育委員会、ハワイ島とアメリカ本土の研究機関が協力して行う、地元の学校への出前授業等を含む宇宙教育プログラムです。写真提供 国立天文台(下記サイトより)
https://www.naoj.org/Topics/2007/05/14/...
総合研究大学院大学物理科学研究科天文科学専攻には、物理科学特別研究(ラボ・ローテーション)という科目があり、最大3つの研究室でそれぞれ1か月程度研究を行うことができます。JAXAにある宇宙科学専攻やKEKにある高エネルギー加速器研究機構の研究室に滞在することも出来ます。普段は三鷹市の国立天文台本部キャンパスにいる大学院生も、すばる望遠鏡光学赤外線観測実習や電波天文観測実習等の科目を履修すれば、実際にハワイ観測所や他の観測所等に行き、観測・データ解析をすることが出来ます。また海外で行われる学会や研究会へも頻繁に参加し発表出来る機会や、総研大全体で募集されている長期(4週間以上6カ月以内)の海外派遣プログラムもあり、若い時から海外の研究者と共同研究をすることも出来ます。
国立天文台には研究者が150人以上(内、総研大天文科学専攻教員100人程度)も在籍しており、天文学を学べる大学院としては海外も含めてスタッフ数としては最大規模でしょう。総研大全体では在学院生数約500名に対して教員数が約1200名と院生数の2倍を超える教員が在籍し、複数教員による指導体制が実現されています。
総研大は、いわゆる大学でのキャンパスライフを過ごしたい方には向きませんが、観測所や研究機関の現場にいる人達に囲まれて研究したい人には良い環境だと思います。
積極的に国際研究会に参加した学生時代が修了後の海外での研究生活につながった
長島薫さん(Max Planck Institute for Solar System Research ポスドク研究員、平成21年度総研大修了)

在学中に研究室にて。
総研大には博士課程3年次編入という形で入学しました。私は学部・修士課程でも一貫して天文学を専攻してきましたが、博士課程ではそれまでの過程で興味を持った「局所的日震学」に取り組むため、日本でほぼ唯一の研究者であった国立天文台の関井隆准教授に指導いただきたいと総研大の門を叩くことになりました。局所的日震学では、太陽表面の振動(音波)を観測することにより、太陽内の音波の伝播時間と伝播時間の距離の関係から、その音波の伝わる太陽の内部の物理量(音速・流れ等)を知ることができます。修士課程で太陽の活動現象の研究に取り組んでいた私は、活動現象の起源に関わる太陽内部を観測的に知る方法として局所的日震学の手法に興味を持ったのでした。
総研大在籍中は国立天文台のひので科学プロジェクトの一員として、当時まだ打ち上げから間もなかった最新鋭の太陽観測衛星「ひので」の運用にも関わらせていただき、自分で観測プログラムを作ったり、そうして得た最新の観測データの解析をしたりして、衛星運用チームの協力のもとに研究を進めることができました。また在籍中は日本学術振興会の特別研究員DC1として採用されていたので、積極的に欧米での研究会にも参加することができました。こうして自分の研究を世界の研究者を前に発表し、共同研究などつながりも持てたことが、修了後の海外でのポスドクというチャンスにつながったとも感じています。
天文科学専攻では、専攻の学生・教員を前に発表を行うコロキウムがありました。各学生は毎年1-2回発表することになりますが、天文学の中でも太陽系・太陽から銀河・宇宙論、装置開発まで様々な専門分野の人がいたので、耳学問として他分野の話を気軽に聞くチャンスでもありました。一方で、主に専門分野内の人を対象とした研究会での発表とは違って、太陽や日震学についてあまり詳しくない他の専門分野の学生にどうやってわかりやすく自分の研究の要点を伝えるかを考える貴重な経験にもなりました。自分の研究トピックだけでなく日震学についてのレビューをしたこともあり、いい勉強になりました。
最先端の研究を進めている若手研究者達と知り合い、共に学び研究できたことが最も価値ある財産。
富田賢吾さん(大阪大学 助教、平成23年度総研大修了)
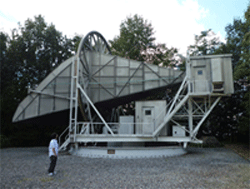
宇宙背景放射を最初に観測したHolmdel Horn Antennaと
さて何故そのような暴挙(?)に出たかと言えば単純で、当時自分で調べた限りやりたいことをやるのに最良の環境だと思われたからです。私は大規模流体シミュレーションを用いた研究に興味があったので国立天文台の保有する大型計算機は大変魅力的でした(注:計算機を初めとして国立天文台の設備は全国共同利用であり、天文台所属だからと言って優先的に利用できるわけではありません)。実際に私は天文台に導入された最新のスーパーコンピュータを用いて原始星形成過程の直接的三次元輻射磁気流体シミュレーションを世界で最初に(かなり条件の多い世界初ですが)成功させ、博士論文を書きました。大学院生の仕事としてはちょっとしたものだと勝手に思っていますが、それも良い環境と共同研究者に恵まれたからこその結果です。また、私の卒業と同時期に稼働する予定であったALMA(アタカマ大型ミリ波サブミリ波干渉計)に何らかの形で関わりたいと考えていたので、その日本の担当機関である国立天文台で研究を行うというのも選択の大きな根拠でした。これもほぼ目論見通りに進み、理論家という立場から複数の観測グループと共同で研究を進めています。研究会や滞在研究で海外に渡航する機会も多くあり、大学院時代から私の研究を国際的に認知してもらえたことも大変良かったと思います。海外学振の派遣先に現所属のプリンストン大学を選んだのも、大学院時代に3週間程滞在したことが一つのきっかけでした。そして何より、層の厚い国立天文台のスタッフ、特に現役で最先端の研究を進めている若手研究者の方々と知り合い、共に学び研究することができたことが総研大で得られた最も価値ある財産ではないかと思います。
というわけで、総研大を選んだのは(少なくとも現時点では)正しい選択だったと考えています。これを読んでいる方が総研大天文科学専攻への入学を検討しているのなら・・・あくまでこれは私の個人的経験ですから、無条件に総研大天文科学専攻をお薦めするわけではありません。ですが、総研大天文科学専攻と国立天文台には多数のスタッフと充実した設備、他機関にはない大規模プロジェクト等、有望な学生のやる気と能力を活かすことができる(かもしれない)環境があります。それを活かす戦略を持つことが幸せな大学院生活とそして将来への鍵ではないかと思います。高々ポスドク風情が偉そうなことを言いましたが、参考になれば幸いです。
求めるものがそこにある。さまざまな大学、分野、幅広い年齢層からなる個性的な集団が総研大。
横山央明さん(東京大学 理学系研究科 准教授、平成6年度総研大修了)
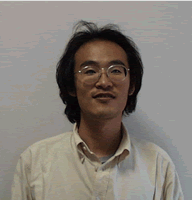
在学当時は太陽物理学研究系に居ました。入学前年に打ち上げられた太陽観測衛星「ようこう」のデータが世界中を驚かせていたころに、まさにその渦中に居たわけです。毎日やってくるデータは、太陽の活発なようすを映す華麗な画像でした。そしてそのデータを求めて世界中から一線級の研究者がひきもきらずにやってきました。また太陽物理学に限らず、一般書や教科書に名前が出てくるような有名な研究者の方が談話会をしてくれたり、講義をしてくれていたのも覚えています。過剰なほどに刺激的な毎日だったのを覚えています。
同期も、さまざまな大学の、いろいろな分野からの、幅広い年齢層の、いい意味での寄せ集めで個性的な人達が集まっていたと思います。わたし自身工学部出身で、入学当初は天文学については素人だったのですが、まわりの友人達とともに学んだかいあって何とかなりました。
総研大の魅力は、「求めるものがそこにある」ということかと思います。とにかく最先端の天文学の、ありとあらゆる分野の、研究グループが、データが、観測機器が、友人達が、すぐそこにある。あとはがっちりかじり付けば、、、将来が開けるかもしれません。
研究者になる夢を実現。最新の天文学に浸って過ごした3年間はとても刺激的。
海老塚 昇さん(理化学研究所先端光学素子開発チーム 研究員、平成6年度総研大修了)
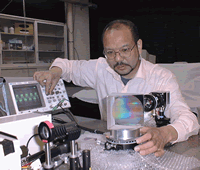
入学当初は理学と工学の文化の違いに戸惑いましたが、様々な背景と持論を持った個性的な教員や院生とともに最新の天文学に浸って過ごした3年間はとても刺激的でした。私は今、8.2mすばる望遠鏡用の回折格子や宇宙望遠鏡用の超軽量ミラー等を開発しています。また、系外地球型惑星探査計画のワーキンググループ等にも参加させていただいております。「30年後の私」を実現してくれた総研大と国立天文台に感謝!
自主性を最大限認めてもらい研究に取り組む。
百瀬宗武さん(茨城大学理学部 教授、平成9年度総研大修了)

また天文台には様々な分野で活躍する専門家が揃っていますから,少し積極的になりさえすれば,理論や他波長観測といった別手法からの有益なアドバイスを受けられます。もちろん,自主性が尊重されればより大きな責任を負うことになりますし,自らを見失ってしまう危険も全く無いとはいえません。しかし明確な目標がある人にとっては,大きな可能性に向かって本当のチャレンジができる場ではないかと思います。
柔軟な発想、分野を横断する知識、高度な専門性と幅広い学識を備えて、研究者を目指す。
布施哲治さん(情報通信研究機構 経営企画部 企画戦略室 プランニングマネージャー 、平成10年度総研大修了)
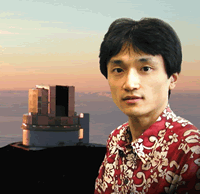
ところが、大学院博士課程を修了しても、研究所や大学等の研究職に就くのは難しいのが現実です。このような時代に求められる研究者──それは奇抜なアイデアと柔軟な発想を持ち、自分の専門だけでなく他の分野の知識も備えた人。総研大での学生生活は、高度な専門性と幅広い学識を備える研究者を目指す皆さんの糧となることでしょう。
総研大で得た知見・経験が複合分野への挑戦を可能に。
梅原広明さん(情報通信研究機構 脳情報通信融合研究センター 研究マネージャー、平成9年度総研大修了)
修士課程までは物理学に属していましたが、それまでも頻繁なご議論を頂いていた谷川清隆氏のもとで、総研大生として三体問題を研究しました。課程修了後は通信総合研究所(現、NICT)に入所し、通信衛星群を形成維持させる将来ミッションに対して、仮想的に衛星間相互作用を加えるような軌道制御を研究しました。
2004年は文部科学省在外研究員として英国へ。欧州で議論を重ねた制御工学研究者のなかには、三体問題・銀河動力学の研究もしている人が少なからずいて励みになりました。帰国後は、制御工学と力学との分野間の相互作用ができそうだという思いに駆られ、再び谷川さんと議論をしています。また、衛星通信用ですが電波工学と軌道力学との融合分野を研究する準備を始めています。総研大に在籍していた頃は私にとって新分野であった天文学の勉強や学位論文執筆で息が切れていたかもしれません。今、総合研究の意義を実感しています。総研大で得た知見・経験が複合分野への挑戦を可能にしています。総研大や国立天文台のゼミなどで作成した、あるいは配られた資料を見直す機会が増えてきました。
最先端の太陽観測衛星「ようこう」に世界中の研究者がアクセス。国際交流と研究を両立。
下条圭美さん(国立天文台 チリ観測所 助教、平成10年度総研大修了)

新たな分野を拓きたい。南極観測も経験。
寺家孝明さん(国立天文台 水沢VLBI観測所 助教、平成13年度総研大修了)
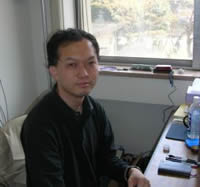
夢と熱意と努力、自然に対する愛情で、人生を豊かに。研究者として成長。
神鳥 亮さん(名古屋市立大学 研究員、平成16年度総研大修了)

宇宙に対する自分の興味、自分は何が好きで何をやりたいのかを、常に意識し続けることは大切だと思います。研究において最終的に頼りになるのは、自分の意思と努力と、自然に対する愛情だけです。博士課程を目指す皆さんは、あえて厳しい選択肢を選ぶ理由についてよく悩んでおくことをお勧めします。常勤の研究職に就ける可能性がゼロに近い現実があるので、「天文学者としての就職」を至上命題に設定する人の大部分は必ず挫折します。大切なのは真剣に研究と取り組む過程の中で自分が成長したり、自分の人生が豊かになることだと思います。そのためにも、自分の専門を深く掘り下げると同時に、学問や社会全体の中での位置づけを常に確認することが重要だと思います。
知の最前線で「ながれ星」を追う。「奇跡」は爆発的な行動力で呼び込むもの。
春日敏測さん(千葉工業大学惑星探査研究センター 研究員、平成17年度総研大修了)

「そうだよ。」
1992年末、深夜ラジオの音楽ヒットチャート。コタツでウトウトしながらも、アーティストの声に即答した。中学生だった。将来は宇宙飛行士、これしかない。興味は仕事につなげましょう。アテ、コネ、実力なんて関係なし。気持ちの昂りが、宇宙科学を人生設計の射程距離にまで近づける。「卒業文集・将来の夢」をマジメに書くなんて照れくさい、10年後の自分なんて想像できませんよ。昼間の道徳授業、担任には言い訳をしながらも、志を固く心に決めていた。
新撰組のふるさと・調布市を南北に縦断する小さな通りに、日本天文学の聖地とよばれる国立天文台がある。そこには総研大生や他大学の院生が所属しており、知の最前線を目指してお互いに切磋琢磨している。研究テーマは多種多様、自分がトップだと誰もが自信に満ち溢れている。でも、知ってる? 聖地で大評判の「ながれ星」って。今までそんな研究はなかったよね。2001、2002年に大出現し、社会現象となった「しし座流星群」は記憶に新しい。彗星や小惑星などの始原天体を起源とするダストが、地球に降り注いで引き起こされる流星群。彼らの一瞬の輝きには、太陽系創世時の壮大なドラマが秘められているのだ。アメリカ航空宇宙局(NASA)は、新時代・始原天体探査としてすぐに着目。世界初となる、航空機からのしし座流星観測ミッション・Leonid MACを打ち出した。2002年、世界中の流星研究者は緊急招集。総研大生・春日も中心メンバーとして、専用航空機(FISTA)に搭乗した。
限りなく宇宙に近い場所から観た「ながれ星」。無数の閃光が夜空に映える。ひとつひとつが奇跡だ。彼らはとおい昔に太陽系の果てで生まれ、この地球までやってきたんだね。まばたきよりも短い時間に、奇跡が繰り返されていく。眩い光に照らしだされ、心が宇宙に写りこむ。中学時代に抱いた願いは、少し違った形でかなえられたようだ。どこかで勝手に走り始めた「カンちがい」は、「昂る気持ち」を糧に熱く燃えはじめ、根拠のない絶大なる自信を確立、爆発的な行動を促し、ついには「奇跡」との出会いをもたらした。そして現在、「ながれ星」というカリスマ天文学の最先端を突き進む上で、大きな支えとなっている。チョットやり過ぎな人生は、今後も厳しい嵐をよぶだろう。必ず克服するけどね。また恩師に年賀状でも書こうかな。10年後の自分は想像をはるかに超えました、って。年の暮れに。あったかいコタツで。
平成15年度、16年度の総研大研究奨励費、平成16年度の総研大海外研究渡航費を受ける。NASA国際航空機しし座流星観測ミッション(Leonid MAC)に関しては、ホームページhttp://leonid.arc.nasa.gov/を参照。